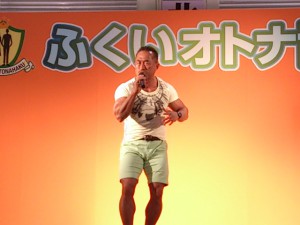© 福井市ウエイトリフティング協会 All rights reserved.

講演会(H26年3月)
先日の日曜ですが、スポーツジャーナリストの二宮清純氏の講演会を拝聴しました。大変感動したので、印象に残っていることだけでもと思い、文章にしました。
あくまでも私の見聞録ですので、表現や内容は二宮氏のものとは正確でないことをあらかじめお断りしておきます。
テーマは「勝者の思考法」
<要旨>
ソチ五輪も終わりましたが、今回選手団団長を務めた橋本聖子さんは、長野五輪超えということを目標にしました。
長野では8個のメダルで、今回は、団体やノルディック複合などさまざまな方面で8個のメダルを獲得しましたが、大変有意義なものがありました。
葛西選手などは、41歳ですよ。41歳にしてなお進化しているんです。ジャンプでは当初は手を回しながら飛んでいたんです。少しでも飛距離を伸ばすために。
それから手を前に出して飛ぶということもありました。札幌五輪では、スキー板を平行に揃えて飛んでいましたね。長野五輪では、日本がメダルを独占しましたが、スキー板はV字に広げていました。それからは、もう変わらない、それが究極の姿であるとも言われました。
しかし今は違うでしょ。スキー板は平行に広げ、手はむささびのように広げていますね。
技術革新には終わりがないんです。トレーニングも同じで、まだまだ発展途上なんです。
このようなイノベーションは、日本人の得意とするところです。葛西選手の姿というものは、我々のあるべき指標を示していると思うんですね。
オリンピック招致活動では、最後に3都市が候補として残りましたが、それぞれに強みと問題がありました。
まずマドリードは人脈力がありました。JOC委員は100人いますが、4割がヨーロッパ系です。そのうち3割はサマランチ会長の息のかかった人たちです。どういうことかというと現在の地位があるのは、サマランチ会長のおかげという人たちが約3割ということです。しかし財政の問題がありました。ファイナンス問題ですね。約27%の失業率があるということで、市民からはオリンピックなんかやっている場合ではないと言われていました。オリンピックは東京でいいという意見もあったほどです。これは日本にとっては願ってもないことでしたね。
次のイスタンブールには、地政学(*1)的な強みがありました。イスタンブールで開催されればイスラム圏初の開催となる。サッカーのワールドカップの開催国は去年は南アフリカ、その次はブラジルです。その次はロシアで次も決まっていてカタールです。みんな新興国なんですね。イスタンブールでオリンピックが開催されればイスラム初となるのです。これはJOCがとりたいと思うのは当然です。
しかし、トルコの南側のシリアが内戦で、化学兵器を使用したとしてアメリカの軍事介入が予想されていた。そうなると大量の難民がトルコ側になだれ込む恐れがある。難民は基本的に救済しなければならないので、難民1人あたり約300万円の経費負担になると言われていたので、5万人いればどうなるか計算してみてください。かなりの財政負担が発生します。
ですから、日本のプレゼンテーションは確かに1番良かったと思うが、他の2都市が勝手にこけただけなのです。
1960年代の東京オリンピックのときのキャッチフレーズは何だったと思いますか。「成長」です。当時の高齢化率は6%くらいですので分かります。2020年にはどうなるでしょう。「成熟」ではないかと思います。その頃の高齢化率は約30%くらいと言われています。3人に1人が高齢者ですよ。1960年代の美徳とされていたことは「効率」です。これが全てにまさる価値観でした。それがスローフーズで温泉にでも入ってゆっくりしましょうとなっていきている。2020年代にはパラダイムシフトが必要。どのように。それは「快適」ではないでしょうか。これは日本だけの問題ではないのです。世界の問題です。今度の東京オリンピックでは、日本がその問題について世界に先駆けて答えなければならないのです。そのようなオリンピックなんです。
最近ではパラリンピックがあまり協調されない。ホスピタリティです。
ロンドン五輪では比較的パラリンピックが重要視された。スーパーでも障害者が購入しやすいように、商品の棚を低くした。高齢者、障害者にやさしい町づくり。これは民間主導で行われなければならない。
パラリンピックはその国の力量が問われるのです。それはホスピタリティであり、心のバリアフリーです。
しかし私も人のことが言えないんです。スポーツジャーナリストなのでイタリアのジャーナリストと名刺交換したんです。そのときにどうして点字がないんですかと言われ、恥じたことがあります。その通りなんですね。日本のジャーナリストや記者も名刺に点字がないんです。
ロンドン五輪のときには、ボランティアとは言わなくてゲームメーカーと呼んだんです。いい言葉だと思いましたね。
誰にでも居場所があり、役割があるんです。だからオリンピックはお祭りだと思う。お神輿もそうでしょ。全員で持ち上げるから軽く持ち上がるんです。一人でも手を抜くと、重く感じるんです。
今度の東京オリンピックでは、人や物が都市に集中することになる。東京中心の考え方になる。現在でもそれが問題視され、地方分権が大事と言われているときに、東京ムーブメントで経済的にも地方にどのように反映させていくのかが課題です。オリンピックは通過点なんです。
よく強化ということが言われる。強化していくとはどういうことか。仕事でもそうですが、城を立てると言っても、いきなり天守閣を建てれるわけがないですね。まずは堀をつくり基礎を造らなければ上は建ちませんね。しっかりした基礎でなければならない。下半身が大事だということです。
私はこれを正三角形の論理と言っています。その中で大事なキーワードは、「普及」、「育成」、「強化」ということです。普及とは農家に例えると、種まきということですね。種をまかなければ実はならないですからね。育成は草刈とか、消毒と水やりとかそのようなことにあたります。強化はおのずと取り入れができる。
ですから底辺がしっかりして広がっていけば、三角形の頂点はおのずと高くなっているんです。
Jリーグの100年構想もそうです。そのようにして選手が育ってきた。いい選手が出てきたんです。それを結果ばかり求めているから逆三角形になる。基礎がしっかりないものはすぐに倒れるんです。
ですから、国体が終わっても続くんです。国体はゴールじゃないんです通過点です。
選択と集中という言葉がありますが、ソチ五輪では日本はいろいろな競技でメダルを取りましたね。これは日本の多様性という特技なんですね。5競技でメダルを取ったということは誇るべきなんですね。アメリカも沢山とりますが、まったく取れない競技もある。中国や韓国なんかも一部の競技しか強くない。
中国なんかは、小さい時に手のレントゲン写真を撮るんです。そしてそれで身長がどれくらい伸びるか分かるので、最初からできる競技とできないものを分けてしまうそうです。
これじゃ選択の権利なんかないですね。人権無視です。
羽生選手が金メダルを取りましたが、これはフィギアスケートの歴史でどれくらいだと思いますか。84年ぶりですよ。それくらいかかるということなんです。
今日は人生の勝利者とは、というテーマですが、それは人それぞれかもしれません。しかし、勝者になるためには、一つ言えることは準備力ということがキーワードだと思います。
日本がオリンピック招致活動でプレゼンテーションのときにフランス語を使用しましたね。JOCの第一公用語は英語じゃないんです。フランス語なんです。2番目が英語です。
オリンピック発生の地から、クオンタリズムを受け継いでいるのは自分たちであるという誇りがあるんです。そこにつけこんだ日本の準備力です。
2000年には、高橋直子が初めて女子マラソンで金メダルを取りましたが、35Kmでスパートをかけたんです。嘘だろと思いました。35km付近からアップダウンが激しくなるんです。2位を走っていたシモンは当然ついていけません。
心の準備ができてないんです。スパートをかけるときにサングラスを投げたんですが、これを誰が拾ったか分かりますか。お父さんです。これだけの人が沿道にいて、偶然お父さんが拾うなんてことあると思いますか。これは完全犯罪なんです。Qちゃんは実行犯でお父さんは共犯です。
最初からしくまれていたんです。それをみごとに遂行したということです。
私は現地で取材をしたかったので小出監督に携帯の番号を教えて欲しいとお願いしたんです。教えてくれたんですが何度かけてもつながらないんです。
後で聞くと35km付近で合宿をしていたそうです。きっと嘘の番号だったのでしょう。
本当に勝ちたかったら大事なことは教えないことです。
北京五輪では、男子400mリレーで銅メダルを取りましたが、朝原選手がキャプテンをつとめていたと思います。短距離でメダルを取るというのは大変なんです。100mを9秒代で走る人って何人いると思いますか。90人ですよ。そのうち88人が黒人です。しかし4人ならばなんとかなるかもしれない。
当時は6チームが失格になったんです。運が良かったといえばそうですが、運だけではないんです。
そのときはちょうど照明が強くてしかも雨だったんですが、どんな環境になるか分かりますか。リレーはある程度選手が走っている前からスタートしますが、そのためにどのくらいから走り出すという目印のテープを貼るんです。照明が強く雨が降ってるんです。当時そのために用意されたのが白いテープです。白いテープは反射して見えにくいんです。そんなものを使用しろと言うんです。
ところが日本は違う色のテープを黙って使用したんです。そんな白いテープを用意するもんが悪いんです。「転ばぬ先の杖」という言葉がありますが、日本には勝つ権利があったんです。勝つためにはどれだけ準備ができているかです。運で勝てるのは子供の運動会です。
パスツールというフランスの科学者がいましたが、「準備なきものには、偶然すら微笑まない」と言った。準備があってはじめて、運も見方してくれるんです。それがないのに偶然は見方してくれないんです。
よくあなたは強運の持ち主だとか言う人がいる。高橋直子がインタビューでそのように言われたことに対して返した言葉が印象的でした。なんと言ったと思いますか。
「24時間は誰にでも与えられた平等な時間ですから」と言ったんです。もし私に1日27時間与えられていて、あなたに24時間しかなかったらそれは私が有利かもしれない。でもすべての人は1日24時間なんだから、私はそれを使って多くの努力をしただけですよと皮肉ったとしか思えない。
スポーツマンであっても、ビジネスの世界でも同じです。それはすべての鉄則です。
私は人生の勝利者とは、時間をうまく使った人だと思う。今私が講演を始めてから約70分がたちましたが、その分皆さんは寿命が70分確実に死に近づいたというのは間違いない事実です。自分の人生振り返ってみて時間に対する後悔がないかどうかです。
事業で失敗したって、なにかで遅れをとっても取り返しがつくでしょ。時間だけは取り返しがつかないんです。
よくあと10年若かったらとか言う人がいるでしょ。そういう人で10年間言い続けた人を知っています。そういう人は結局何も変わらないんです。
時間は試練です。試練を磨き上げて資産にできるかどうか、これにかかっているんです。
人間には2通りある。
「追い込まれる人」と「追い込む人」です。追い込まれる人とは弱い人です。追い込む人は強い人だということです。
今回のソチ五輪で、浅田真央が最後最高の演技をした。監督はすべる前にこういったそうです。「リングで倒れたら、俺が助けに行ってやるから思い切ってやってこい」こんな頼もしい言葉があるでしょうか。浅田真央は追い込まれていた。この言葉ですべてが踏ん切れたと言われる。
よくオリンピックには魔物がいると言われる。あの井上康生が監督にたずねたときに、「それは負けた者が言うセリフだ」と言われ、井上から魔物が消えたと言われる。
小出監督がある大会のときにコースを下見したとき、途中狭くなっているところがあり、キケンだから決してあわてないようにと注意したそうですが、やはりころんでしまったそうです。そのときに選手がすみませんでした私の不注意ですと謝ってきたそうですが、小出監督は、どういったか。すべて私の責任だ許してくれと言ったそうです。
さすがに私もそれは違うんじゃないんですか。あれだけ監督が注意したのに、守らなかった選手の責任でしょと言ったのですが、そのときの監督の言葉に背筋が寒くなりました。
「何をいってるんだ、人を育てるということはそんなやさしいことじゃないんだ。私が5回言って分からなければ10回言わなければならない。10回言ってわかななければ15回言わなければならない。責任者たるものは、伝えるだけでなくて、ちゃんと選手に伝わったかどうか見極めるところまでが義務なんだと言われました。
そのとき私はどうしてこの人の元で選手が育つのか理解できました。
王家の帝王学(*2)でこういう言葉があります。
「今きみたちがリーダーとしてどうあるべきかを知るならば、最後まで読んで欲しい。
Il bello dorso
よきリーダーたらんとするものは、まずよき背中をもちなさい。帝王学はまずここからスタートしているんです。
子供は親のどこを見て育っているのか知っているか?
それは顔ではない、背中なんだ。
生徒は教師のどこを見ているのか?
それは顔ではない、背中なんだ。
選手はコーチや監督のどこをみているか?
それは顔ではない、背中なんだ。
部下は上司のどこをみているか?
それは顔ではない、背中なんだ。
私は今日本で一番いい背中を持っているのは、澤穂希だと思う、彼女は、後輩に「辛くなったら私の背中を見なさい」と言っているそうだ。
そして彼女の背中は違う、「暗がりの中の灯台だ」と言われている。中心なき組織は機能しないんです。
(*1) 地政学、すなわち、地理と政治や軍事との関係性についての研究は、すでに古代ギリシアの時代、ヘロドトスの『歴史』にその起源が読み取れる。彼は民族の命運が地理的な環境と深く関係していることをペルシア戦争の研究から述べている。
(*2)
帝王学(ていおうがく)とは、王家や伝統ある家系・家柄などの特別な地位の跡継ぎに対する、幼少時から家督を継承するまでの特別教育を指す。学と名はついているが明確な定義のある学問ではなく、一般人における教育には該当しない。
具体的には突き詰めたリーダーシップ論とでも言うべきものである。経営術や部下を統制する方法といった限定的なものではなく、様々な幅広い知識・経験・作法など、跡継ぎとしての人格や人間形成に到るまでをも含む全人的教育である。
また、いわゆる学校での教育という概念とは根本的に異なり、自分の家系を後世へ存続させ繁栄させる、という使命感を植えつけることを目的としている。