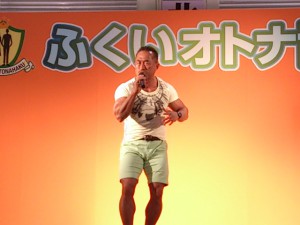© 福井市ウエイトリフティング協会 All rights reserved.
免疫とアレルギー
へっくしょぉ~い
という程度なら良いのですが、アレルギーってのは、ひどい場合にはショック死する場合もある恐い病です。
ということで、アレルギーがなんで起こるのかを免疫の方からみてみましょう(ーー)ジィ~
まず、アレルギーには4種類あるそうです。
1型から4型まで分けられています。
簡単にそれぞれがどのような過程を経るのかみてみませう。
4種類の内、1~3型は主に抗体が関与するもので、4型はT細胞が関与すると言うことです。
一番多いのが1型でして、抗原が粘膜等から体内に入ってきますと、この1型に非常に強く関与するIgEが作られ、この抗体がマスト細胞(肥満細胞)がもっているレセプターと結合します。ここに抗原が結合しますと、抗体からの信号でマスト細胞がヒスタミン等の化合物を作り出して放出し、これが炎症を起こします。
疾患としては、喘息・じん麻疹・鼻炎・花粉症・アナフィラキシーショック等が1型アレルギーによって引き起こされます。
2型は、自分自身の細胞に結合した抗体が補体系を活性化させる事によって生体に障害を与えるパターンで、疾患としては、Rh不適合・自己免疫性溶血性貧血・バセドウ病等がこの2型アレルギーで引き起こされます。
3型は、生体内で生じた、抗原・抗体複合体(くっついたやつですね)が、細胞に沈着して、それが補体系を活性化して起こるそうで、疾患としては、全身性エリテマトーデス・食品アレルギーの一部等があるそうです。
4型は、抗原がT細胞を活性化する事によっておこるもので、疾患としては、結核・真菌・ウィルス等の感染症、脊髄炎、脳炎、慢性関節リウマチ・甲状腺炎等があるそうです。
この中で、一般的に「アレルギー」と私達が言っているのは1型アレルギーに含まれているみたいですね。
自己免疫疾患(後述)というグループに属する物ありますが、アレルギーというのは、基本的に、細胞を破壊して生体に障害を与えるという事のようです。
抗体が関与するアレルギーは、「即時型」と言われ、短時間に発症します。
これに対して、細胞が関与するのは「遅延型」と言われ、少し時間をおいて発症するそうで、4型がこれになります。
このアレルギーの原因となるIgEは日本の石坂公成氏によって発見されました。
さて、アレルギーには、前述の様に、その発生メカニズムによる分類があるのですが、私達が一般的に「アレルギー」としておつき合いしているのは、1型の物が多いと思います。
ということで、この1型のアレルギーを詳しくみてみたいと思います。
抗原が侵入してきますと、抗原提示細胞(マクロファージなど)がそれを取り込みます。この時、この抗原と結合できるB細胞もこの抗原と結合します。
抗原提示細胞はヘルパーT細胞へ情報提示を行い、これを受け取ったヘルパーT細胞は、IL-4を作りだし、この抗原と結合できるB細胞を活性化させます。
このIL-4の働きで、IgEの生産が容易になります。
B細胞はこうしてIgEを血中に放ちます。
マスト細胞(肥満細胞)の表面には、このIgEを受けとめる特異的なレセプターをもっていて、IgEはこのレセプターと結合してマスト細胞にくっつきます。
●-
こんな感じでしょうか(^^;
実際にはマスト細胞表面にレセプターはたくさんあります。
ここに抗原がやってきますと、結合している抗体にブリッジ構造を作るように結合します。
◎
Y Y
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
マスト細胞
このブリッジ構造が出来るまでは、マスト細胞では何も起こりません。
しかし、抗原がやってきて、ブリッジ構造が出来上がると、マスト細胞の表面に変化が起こるらしくこれを信号としマスト細胞が変化するそうです。
細胞膜のリン酸脂質である、アラキドン酸というのが、遊離してこれが代謝によって、最終的にロイコトリエンやプロスタグランジンという物質になるんだそうです。
このロイコトリエンというのは、血管に作用して気管支を収縮させる働きがあり、プロスタグランジンの方は、気管支の筋肉を収縮させる働きがあるそうです。
これらが、血管や腸管等の通って、喘息や皮膚炎等の症状を引き起こすそうです。
マスト細胞の表面にブリッジ構造が出来上がりますと、もう一つマスト細胞内で変化が起こります。
小胞体に信号が送られ、カルシウムが大量に生成され、細胞を作っている骨格タンパク質が活性化して、顆粒球が細胞表面にまで移動して、分泌物を出します。
こうして作られるのが、ヒスタミンやペパリンと呼ばれている物質達です。
マスト細胞は、粘膜にある物と、組織にある物の2種類があるそうですが、性格が全く違うそうで、IgEレセプターの数は、圧倒的に粘膜中に多く存在しているそうです。
このマスト細胞は、サイトカインも放出するそうです。
このマスト細胞や他のリンパ細胞によって、好酸球がお呼ばれされます(^^;
好酸球もIgEレセプターを持っていて、マスト細胞と同じ様な化学物質を作り出しますので、このお呼ばれされた好酸球がアレルギー症状の慢性化に関与しているんだそうです。
これら、マスト細胞の作用で作り出される物質の起こす症状は大体以下の通り。
IL-5・IL-8:好中球・好酸球・好塩基球を誘引する
ヒスタミン :血管拡張と血管浸透性冗長・気管支の収縮
PFA :微小血栓
トリプターゼ :蛋白質分解酵素がC3(補体)を活性化
PGD2 :粘膜浮腫
LTC4・LTD4 :粘液分泌
このアレルギーが起こる仕組みだけをみますと、誰でもアレルギーを起こしそうですが、実際はそうなっていません。
なぜでしょう(・・?
血清中のIgE値が異常に高い人の場合、ほとんどがアトピー性皮膚炎・喘息・鼻炎等のアレルギー症状を示しているそうです。
これは、ヘルパーT細胞に変化が起こって、IgEの生産を促進するIL-4が過剰に作られていたり、B細胞中の免疫グロブリン遺伝子に変化が生じて通常より多くIgEを作ってしまうという事のようです。
T細胞には、サプレッサーT細胞ってのがあるということが判っているようですが、どうもこれの機能のバランスの崩れがアレルギーの原因のようです。
抗原提示細胞からヘルパーT細胞へ抗原提示がありますと、サイトカインで指令が出されB細胞が成熟して抗体を放出したり、抗体の刺激を受け取った、マスト細胞や好酸球が化学物質を放出したりします。
基本はこのT細胞への抗原提示が行われることが、アレルギー発症のきっかけになります。
しかし、同時に、サプレッサーとして働くT細胞からは、IFN-γというサイトカインが放出されまして、T細胞のサイトカイン放出が抑制されます。このIFN-γは同時にB細胞にも作用して、抗体生成を抑制します。
ここで面白いのは、ヘルパーT細胞が抗原提示されると放出するIL-10というサイトカインがあるのですが、これは、このサプレッサー作用をするT細胞の動きを抑制します。
ですから、この反応系は互いに互いを監視し合う、微妙なバランスの上に成り立っているのだそうです。
ということで、この2種類のT細胞の存在比のバランスが崩れると、アレルギーを発症することになるようです。
また、アレルギーは遺伝的要素が関係している事が判っているそうでして、
非アトピー母+非アトピー父=10%(子アトピー確率)
非アトピー母+アトピー父 =30%
アトピー母+非アトピー父 =30%
アトピー母+アトピー父 =60~80%
と、明らかな相関関係が認められるようです。
「アトピー」というのは、アレルギーの中でもIgEが関与している1型のアレルギーで、このIgEを遺伝的に作りやすい素因の事だそうです。
現在、このアトピー遺伝子を探す研究が進んでいるそうですが、実際には単一的な遺伝子で起こっているのではないようです。
今のところ、マスト細胞のIgEレセプター遺伝子のβ鎖の変異がある人にアレルギー発生率が高いことが判っているそうですが、なぜ変異が起こるのかは判っていないようです。
このほかにも、IgEの生産を促進するIL-4の遺伝子も関連しているようです。
しかし、このIgEが絡んだ免疫系ってのは、知れば知るほど、悪影響しか及ぼしていない様にしか思えないのですが、なんでこんな仕組みをもっているのでしょうか?
以前、寄生虫の話の中で、アレルギーと寄生虫の話がありましたが、あれはどのようにここでは、考えられるかと言いますと、このIgEとマスト細胞の反応系は、元々は寄生虫に対する防御系だった・・・・、ということです(^^;
相手が居なくなってしまったので、何を思ったのか、自分自身を相手に選んでしまっていると言うことのようです(^^;;;;
アレルギーの治療としては、各段階でのつながりを断ち切るという事になるようですが、現在、1型アレルギーの治療方法として、分子遺伝学の研究から、マスト細胞にIgEが結合できなくしてしまう方法があみ出されているそうでして、基礎実験的には成功しているようで、実用化に向けて、進んではいるようです(^^)