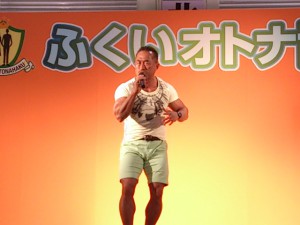© 福井市ウエイトリフティング協会 All rights reserved.
腸管免疫
普通、免疫と言いますと、リンパ管!とか思いまして、ちょっと知ってると、秘蔵・・・・脾臓とか胸腺とか思うわけですが、もっとでかい免疫に 関わる器官があるのは意外と知られていません(・・?
結構気軽に切り取ってしまう器官(^^;に虫垂があります。 確かに、切り取ってしまっても、特に変化を生じません。
ん??? 切り取っても変化しないという臓器の話をどこかでしましたね(^^;そう、胸腺でした。 虫垂は、免疫系組織の塊みたいな臓器(?)だそうです。
じゃ、とってしまって問題ないのかと言いますと、問題ないんです。ちゃんと、代わりを勤める器官があるのです。
そう、長官です。下の物がこけたらやはり上の人が・・・・じゃなくて(^^;
;; 腸管です(^^;
ここで働いているのは、腸管免疫という特殊な免疫機構です。
最初に書きましたが、腸の中には非自己蛋白質が山のようにやってきます。
これを片っ端から非自己として対処されてはたまりません(^^;
ということで、腸管では、ちょっと他とは違った免疫が働いています。覗きに行っても良いのですが、にほいますので(^^;、表から観察しましょう。
カビの話の時に、体内には沢山の細菌が生息していて、正常菌嚢というのを作っていて、他の菌が入り込むのを防いでいるという話を書きましたが、腸の中はまさにその状態です。
ですから、生体防御という点では、この腸内細菌達が最初の障壁として働いています。
では、生体側の防御はどうなっているのかと言いますと、食物が腸管に来ますと、当然、抗原として腸管免疫系は刺激を受けます。
パイエル板と言われる組織や腸管上皮内のリンパ球が刺激を受けるらしく、ここでIgAを作り出すB細胞が作り出され、腸管粘膜の粘膜固有層や乳腺、涙腺というところにやってきて、IgAが作り出され、これらのIgAは、腸管上皮細胞(消化吸収をする細胞)の中で作られた運搬タンパク質と結合して、腸管腔(食べ物が通っているところ)に運ばれ、腸壁からそのまま直接体内に入ろうとする、外来品を懲らしめます(^^; このほかにも、この腸管免疫に携わっているT細胞は、抗原提示等の刺激を受けなくても、非自己が来ればすぐに活性化するような物が揃っているそうです。
さて、ここで一番最初に出てきた謎がむくむくと頭を持ち上げてきます。
栄養素として取り込まれてくる異物への反応です。
これら栄養素としてのタンパク質に対しては免疫系は排除に動きません。
このことを「経口免疫寛容」と言うそうです。後ほど触れますが、この免疫寛容を使った病気の治療が現在行われ始めています。
この仕組みはまだ完全に解明されてはいないようですが、TGFβというサイトカインの二律背反の作用が原因と考えられているようです。
腸管粘膜を突破して侵入を謀ろうとする異物に対応しているのが分泌型IgAなのですが、これをB細胞に作らせる作用をするのが、TGFβだそうです。ところがこのTGFβは、これ以外の細胞に対して免疫抑制の作用をするんだそうで、これによって、分泌型IgAは増えますが、他の免疫系はおとなしくなるという効果を発揮するらしいです。
非常に微妙なバランスの上に成り立っているこのシステムですが、このバ ランスが崩れますと、免疫系が通常と同じ反応を示してIgE抗体を作り出してしまい、卵がだめとか牛乳がだめとかいう食餌アレルギーを起こしてしまう事になります。
さて、かなり抜けはある上に、不明瞭な文章で免疫機能の中身を書いてき ましたが、これら免疫が絡んだ病気のお話に移りたいと思います。
しかし、免疫という機能をみてみると免疫があらゆる病気に絡んでいるとも言えそうな気もします(^^;
まずは病気というよりは、みなさんよぉくご存じのやつから行ってみたいと思います。
免疫というのは、非自己の排除ということで、自己と非自己の区別はMHCの型で行われているということでした。
さて、ここで?に思うことがありませんか? 免疫の主役達は血流に乗って体内を巡回しています。
皆さん「血」と言ったら何を思い浮かべますでしょうか?
一番最初に思い浮かべるのは赤血球だと思うのですが、私達は「輸血」という行為をごく当たり前に考えています。
他人の細胞、すなわち非自己を取り込むわけですから、当然免疫機能が働くはずです。
自己を決定しているMHCの型が一致するのは数万~数十万人に一人とい う確率だということも書いたと思います。
しかし、一般的な輸血ではこの様な希な一致を待たずして、簡単に輸血が行われています。
なんで、大丈夫なんでしょうか(・・? 私達は血液と言いますと、ABO型(後はRh型でしょうか)さえ一致していれば、輸血は可能ということを知っています。
ちょっと、このあたりを攻めてみましょう(^^; 血液型は1901年に発見され、当時はABCという型に分けられたそうですが、1年後にAB型が発見され、C型はAの要素もBの要素ももって いないと言うことで0型(ゼロです(^^;)と名付けられました。
輸血の主な目的は赤血球の移入ですが、この赤血球の誕生過程に秘密があります。
赤血球も白血球などと同じ、骨髄の幹細胞から生まれてくるのですが、そ の成熟のプロセスで、赤血球は核等の細胞の主要成分のほとんどを捨ててしまいます。この時に自己証明書であるHLAも捨ててしまうのです。
ということで、輸血の時にHLAが問題にならなくなるのだそうです。
しかし、血液中のリンパ球や好中球やマクロファージのHLA抗原は高濃度に備わってますので、そこで問題になるのが赤血球表面の化学構造で、 これが血液型と呼ばれる「型抗原」なんだそうです。
一番知られてる強い型抗原としてはABO型、弱い型抗原としてはRh型を初めとして多くの物があります。
一般に問題になるのはこのABOとRhの型です。 A型の人はA型抗原、B型の人はB型抗原、AB型の人にはA型抗原・B型抗原が備わっていて、O型の人にはH抗原があります。 血液中の抗体を見ると、A型の人には抗B抗体、B型の人には抗A抗体、O型の人には抗A抗体・抗B抗体両方があり、AB型の人はどちらも存在 しないそうです。
A型の血液をB型の人に輸血するとどうなるかと言いますと、B型血液中 にある抗A抗体がA型抗原と結合し赤血球の固まりをつくり(凝集といいます)、補体と協力してA型赤血球を溶かしてしまいます。
で、時々O型の血液はどの人にも輸血できると信じている方がいるようですが、O型血液中には、抗A抗体・抗B抗体がどちらもありますので、輸血を受けた側のA型抗原やB型抗原とトラブルを起こします。
もう一つ有名なのがRh型です。
ちなみに私はマイナスです(^^;タイセツニホゴシテクダサイ
この型の場合は、Rhプラス抗原とRhマイナス抗原をもっているかどうかの違いですが、これもABOと同じ様なトラブルを起こしますので、輸 血の際には一致している事が条件になります。
日本人の場合、Rhマイナスの人の比率は0.5%程度とのことです。 このRh型で注意しなくてはならないのは、Rh+の男性とRh-の女性が子どもをつくるときです。 胎児の段階では、母体と胎盤という薄い膜を通して血液成分が胎児・母胎間を行き来しています。
この往来の中で、胎児のRh抗原がRh-の母親に吸収されますと、母胎 側に抗Rh抗体が作られます。
この抗Rh抗体が今度は胎児側に入りますと、胎児のRh抗原と反応を起こして、赤血球が破壊され黄疸をおこし、死産や流産ということになりかねません。
この反応は初産の時には弱く、この様な状況なることは希の様ですが、2番目の子どもになると、既に抗Rh抗体が存在する胎内にいることになりますので、抗Rh抗体が胎盤を通して胎児に受け継がれてしまい、赤血球や骨髄にある未熟な赤血球のRh抗原とトラブルを起こしてしまいます。
このトラブルに対処するには、最初の子どももそれ以降の子どもも、母親由来の抗Rh抗体や損傷された赤血球を全面的に入れ替えなくてはなりません。
この「全血交換」では、抗体の出来ていないRh-の血液を大量に輸血して抗体を薄めてしまうのだそうです。
その後、赤ちゃんの体内では新陳代謝でRh-の血液は少しづつ捨てられ、本来のRh+の血液に変わってしまうそうです。