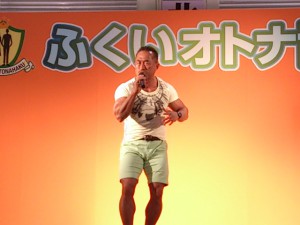© 福井市ウエイトリフティング協会 All rights reserved.
骨粗鬆症の定義
【骨粗鬆症の定義】
骨が減少するのを何でも骨粗鬆症と言うかといいますとちと違うようです。
骨粗鬆症という病気は、骨が減少する病気なんですが、その定義の一つに「普通の骨の成分が変わっていない場合」のみに使用される言葉というのがあるそうでして、他にも骨が減少する病気があるんだそうです。
例えば、癌が骨にまで拡がりますと、骨の一部を置き換えてしまう場合があるそうで、骨の成分が変わってしまっていますので、骨粗鬆症とは呼ばないそうですし、骨軟化症という病気では、骨の土台になるタンパク質の部分は沢山出来るらしいのですが、これにカルシウムやリン酸等のミネラルがつけ加わって固まることがないために骨が柔らかくなってしまうそうでして、これも骨の成分はミネラルの減少という普通の骨と違う物なので、骨粗鬆症という名前にはならないそうです。
さて、「骨量を測る」と言うのはつい数年前までは夢のような事だったのだそうです。
え?レントゲン写真で判るんじゃないの???と、私達素人は簡単に思いますがそうでもないようです(^^;
骨を切り取って分析すれば、カルシウムや各ミネラル、コラーゲン線維がどれだけあるかを分析することは出来ますが、「骨出しな」「ほいよっ」
ってな具合でとれるわけではありません(^^;
はっきり言って手術です(^^;;;;
で、体の外から骨の量を測定する・・・・・これを非侵襲的な骨量測定というそうですが、やっぱレントゲン写真・・・・と私達は思うわけです(^^;そう。確かにX線を利用した測定を行うらしいのですが、レントゲン写真なんてのはここ数年で登場した技術ではありません。にもかかわらず、数年前まで骨量を測定することが夢のような事だったとはこれいかに(・・????
ということで・・・・・
物理の時間です(^O^;
ここで、X線発生装置の話からスタートするとえらく長い文章になりますので書きません(^^;一般にレントゲン写真と言われている物がなんでぎゃぁ~こつを映し出せるかですが、X線という高エネルギー電磁波が可視光よりも物質への透過力が強いからですが、そんな中で物質の密度によってこの放射線の通り具
合が違う事を利用しているわけです。
一般に、ミネラルや金属はあまり放射線を通しません。水はそこそこ通しますが、脂肪は水よりも更によく通るそうです。
大体、この3種類の透過性に分けられまして、ミネラルの場合、その量が多ければ多いほど放射線を遮断します。
だもんで、レントゲン写真で骨の形が写真に写ったときにはこれで骨量が判るぅ~\(^O^)/と思ったのは無理もないことなんですが・・・・・ということです(^^;
で、正確な骨量の測定が出来る様になるまで、普通のレントゲン写真で「骨量を測ることが出来ない」という事が判っていたのではなく、気づいていなかったというのが実態のようです(^^;;;;;
正確な骨量測定が出来るようになり、普通のレントゲン写真から骨が減っていると判定された人の実際の骨量を調べてみると50%の減少になっていたそうで、それよりも症状の軽い40%とか20%とかの減少の人の場合、普通のレントゲン写真ではまったく判らないということが明らかになりました(^^;さてなぜでしょう?????(・_・)??????
ワープロ検定の時間ですヾ(^^;ヲヒヲヒ
例えば、キーボードによる日本語入力の場合。
一時間で万単位の文字数を入力してしまうような人から、同じ一時間に数十文字しか入力できない初心者までが混ざった集団に、ある文章を入力して貰い、その平均時間からその文章に含まれている変換が非常に難しい文字、すなわち障害となるような物がどれだけ含まれているかを知ることは不可能です(^^;
これが、通常のレントゲン写真のパターンです。
そこに障害物があることは判るのですが、どの程度あるのかが判らない。そこであみ出されたのが、同じレベルの人に打って貰う方法(^^;
SXA(単一エネルギーX線吸収法)というもので、これだとどの程度の障害物があるかが判ります。
ただこれの場合、比較的体の表面に近い場所の骨には有効らしいのですが、背骨の様な結構深いところにある物の場合、腹部に臓器や脂肪などがいろいろあるために、阻害率の違う障害物が多々存在します。
そこで、現在一番よく利用されているのがDXA(二重エネルギーX線吸収法)と言われる物で、2種類のエネルギーのX線を使って調べる方法だそうで、これらの方法ですと、発生源で作られたX線の一部を取り出して使用するので、被爆の危険性も通常のX線撮影よりも少なく済むそうです。
しかし、完全な骨量測定法というところまでにはまだまだ長い道のりが残っているそうです。
何が問題かと言いますと、先に書きましたが、骨は2つの部分から出来上がっています。外側の固い皮質骨と内側の海綿のような海綿骨。その割合は骨の形で違うそうですが、DXA法では、この2種類の骨を通過してくるX線を無差別に受けとめて測定していますので、一体どれだけが皮質骨に吸収され、どれだけが海綿骨に吸収されたのかが判らないのだそうです。
そこで、登場したのが、QCT(定量的コンピュータ断層法)というのを骨量測定に応用した物なんだそうですが、背骨に関しては充分に正確な方
法がまだ無く、卵巣などへの被爆量が多く、病気の診断以外では一般の検診に利用するのに問題があるそうでして。
ということで、腕の方にも応用できるQCTが開発されたそうで、pQCT(末梢型QCT)と呼ばれているそうです。
QCTでは皮質骨・海綿骨をそれぞれ別々に測定できます。皮質骨は骨に強さを与える物で年齢と共に徐々に減少します。海綿骨は更年期になると急に減少するそうで、表面積が大きいことから薬や栄養、運動の影響をかなり受けるようで、この二つの骨を区別して測定できることによって、若
年層の人の今後の骨の減少の危険を予測することや、栄養状態や薬の骨に対する影響を調べるのに非常に役に立っているそうです。