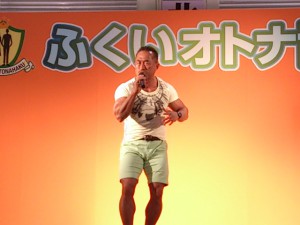© 福井市ウエイトリフティング協会 All rights reserved.
脂肪の取りすぎは本当に体に悪いのか?
「週間現代」に以下のような記事がありますので紹介します。 桜美林大学の柴田博教授の疫学調査や、欧米各国のデータでも明らかにコレス テロールの値が低い人は、ガンになるリスクが高くなるということを述べてい ます。
なお、出典が週刊誌ということで、分析不足というか、内容が恣意的と感じられ ることも否定できないが、興味ある結果である。
———————————————————————-
「コレステロールは、細胞膜、副腎皮質ホルモン、性ホルモンの大切な原料に なるだけでなく、ガンになるリスクを低くする。
埼玉県戸田市の40~80歳の男女住民3222人を対象に行った。十年間にもわ たる追跡調査。
被験者をコレステロール値が低いグループ1、中間のグループ2、高いグルー プ3、の三種に分け、グループ1の癌死の危険度を1としたとき、他のグルー プの癌死の危険度がどのくらいになるかを調べた。
その結果、女性の場合、
グループ2の癌死の相対危険度は0.6、
グループ3は0.76
となり、つまり2はコレステロール値が低い1より0.4ポイントグループ3で 1より0.24ポイントも危険度が低いというデータが得られた。
男性も、2は0.66で、やはり1より癌死の危険度が低いという結果が出たので ある。(ただし3は1.10、1より0.1ポイント危険度が高い)。
同種の研究は他にもある。筑波大学社会医学系の磯博康助教授が、大阪府八尾 市在住の40~69歳の男女1万2千人を9年間、追跡調査したデータだ。コ レステロール値を以下の男女別5段階に分け、それぞれの癌死亡者の割合を男 女別に導き出している。男性の結果、
160mg/d以下l3.79%、
160~179、2.54%
180~199、2.71%
200~219、2.35%
220以上、2.16%
コレステロール値が低くなるほど、癌死亡率が高くなる傾向が読みとれる。秋 田で実施した調査、日米欧8カ国、約63万人分のデータをまとめたアメリカ のミネソタ大学などの研究報告でも、同じ傾向がはっきりと現れているので す。
国民のコレステロール値が世界一高いといわれるフィンランドのマルドーン博 士の研究結果は衝撃的だ。
薬物などでコレステロール値を下げた人たちと、何も治療をしなかった人のグ ループの比較調査を試みている。治療によりコレステロール値を下げたグルー プの人間の様々な要因による死亡率を、治療を行わなかったグループの人間の 死亡率で割ってみる。
結果は冠動脈疾患死こそ0.85で危険度は下がっている が、癌死の危険度は1.43と、43%もアップしている。
さらに、危険度が高まっ ているのが、「疾患と無関係の死」だ。
これは病気以外の原因、自殺、 事故などによる死を表している。コレステロール値を下げることと、これら 「疾患と無関係の死」 の増加には、何らかの因果関係があるのだろうか。前出の柴田教授は、その可 能性は大いにあると断言する
。 「アメリカの学者の研究で低コレステロールがうつ病の引き金になることがわ かっている」そして、これら癌、自殺のさまざまな要因によって、コレステ ロール値を下げたグループの総死亡率の相対危険度は、何も行わなかったグ ループに対して、1.07という数字になった。
コレステロール値が低すぎると、死亡率が高まる疾患がいくつもある。がん、 脳出血、肝疾患、自殺(詳細は、「脂肪は最高のエネルギー源?」を)など。
しかし、上昇すれば、心筋梗塞、脳梗塞の危険性は高まるといことも忘れてはならない」
———————————————————————-
しかし、統計学的には、これらの数字は、誤差を考えると同程度だとか
なんだ早く言えってか!
ところで、コレステロール値が高すぎる場合はどしたらいいのだろうか? 食事の面から言えば、植物性食用油などには、それに含まれる植物性ステロールが、胆汁酸に溶け込んで、 コレステロールの小腸からの吸収をおさえる効果があるそうだ。
また、大豆タンパクにも、同じような効果があるそうだ。